 2月は節分ですね。
2月は節分ですね。
2026年の節分は2月3日(火)
この記事では幼稚園・小学校受験を意識した節分の過ごし方をお話ししたいと思います。

ではさっそくいきましょう。
✔ この記事の信頼性
小学校受験専門塾で25年間の指導経験がある現役講師
職業柄、伝統的な季節の風習や行事には敏感
本記事の内容
- 鬼のお面作り
- 豆まき
- 恵方巻作り
- 神社などに出かける
- 本の読み聞かせ
節分:9か月後の受験まで忘れないために強力インプットしたい

✅節分は2月
✅受験本番は10~12月
8か月以上も先ですね。
お子さんの心にしっかり留まる体験をしておきたいです。

その理由とは?
・
・
受験で出題される冬のものは春・夏・秋に比べて数が少ないため、「節分」は出題頻度が高め。冬の行事だとしっかり記憶しておかなければならない大事なものだからです。
受験で出題される冬のもの
クリスマス
お正月(鏡餅、門松、羽根つき、たこあげ、こま回し、おせち料理、お雑煮)
雪だるま、かまくら、スキー
つばき、シクラメン
みかん
節分
ほかの季節に比べて圧倒的に数が少ない!
クリスマスやお正月、雪は「冬」だとわかりやすすぎる!
出題者側からすると「節分」くらいが難易度的にも丁度よいのでしょう。
節分を楽しみながら受験対策にもなる5つのことは?

①鬼のお面作り
幼稚園・保育園や幼児教室で、一度は鬼のお面を作ったことがあるのではないでしょうか?

↑ この鬼クンを模写して描くだけでもかなり有意義な学習になりますよ~
描く・切る・貼る・塗る・留める、輪ゴムつなぎ、穴あけ、ホッチキス留め・・・・
いろいろと工夫できますね。
お面作りは巧緻性の集大成!
親子で記念に残る作品を作り、目につく場所に保管しておけば、ばっちり記憶にも残るでしょう。
②豆まき
鬼は~外、福は~内
元気よく豆まきをしたあとも学習ができます。
✅パパ、ママ、きょうだいの年の数だけ、お皿にお豆を用意するのはボク(ワタシ)のお仕事です。じーじ、ばーばもご一緒ならけっして楽な任務ではありません。
✅家族みんなでお豆はお箸で食べませんか?割り箸なら簡単。塗り箸だと親もけっこう大変かも?
✅さらに残っているお豆があるなら、家族全員に同じ数ずつ分けてもらいましょう。どうやるのがいいのかな?頭を使いますね。
↓ せっかくなら本格的に豆はマスに入れたい ↓
③恵方巻作り
お子さんと一緒に楽しみながら作りましょう。
✅米をとぐ(ざるを使って名称も覚えます。)
✅材料を切る(子供用包丁を買ってあげると張り切ってくれるかも。)
✅具材をのせて巻く(まっすぐ巻くのは技術が必要です。ゆっくりゆっくり・・・)
完成した恵方巻♪

そのままかぶりつくのもいいですが、切って食べるなら、ぜひお子さんに切ってもらいましょう。
一回でじょうずにできるかな?
★4人家族で4等分する場合→まず半分に切ってから、そのまた半分・・の順序ですね。
★3人家族で3等分する場合→難しいですね。いきなり切るのではなく、予測をして切りましょうね。
記念写真を忘れずに!
時間が経っても写真を見ればそのときのことを思い出せます。
④神社などに出かける
神社などで豆まき行事を大々的にやるなら、出かけてみるのも良いですね。
非日常の体験は記憶に強く残ることでしょう。
神社では「鳥居」「境内」などの単語を意識的に使いましょう。
特に「鳥居」はよく出題されます。
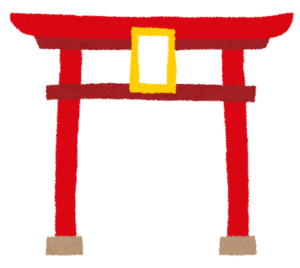
➄本の読み聞かせ
節分の絵本はいろいろあります。
いくつかご紹介しておきます。
まとめ

以上「受験を意識した節分の過ごし方」でした。
ご参考になれば幸いです。
幼少期に家族で季節の行事をした記憶は、大きくなっても懐かしい記憶として残り、自分が愛されてきた証となるものです。
お忙しい毎日でしょうが、ぜひとも時間を作ってご家族お揃いでできるといいなと個人的に思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。





